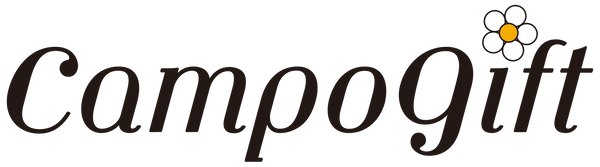【小暑】7/7〜7/22
ちょうど七夕の短冊に願いを込めるこの時期。暦の上では、次の大暑にかけて「暑さのピーク」に向かう、「暑中」の始まりの頃。
梅雨明けとともに、暑さもいよいよ本格的になってきます。
夏祭りなどのイベントも開催され、気持ちも自然と明るくなりますが、その反面、そわそわして落ち着かなくなったり、眠りが浅くなったりと、「心(しん)」に熱がこもることで起こる不調が気になることも。
そんな小暑の養生ポイントは、夏の五臓である「心(しん)」を養うこと。そして、高温多湿の影響で体にこもった“熱”と“湿”を外へ逃がしてあげることも大切です。
小暑に起こりやすい不調
⚫︎心の不調
漢方でいう「心(しん)」とは、全身に血液を送る心臓の働きだけでなく、文字通り「こころ(精神・睡眠)」をコントロールする役割もあるとされています。
たとえば、好きな人を想って胸がキュンと熱くなったり、緊張で心臓がドキドキしたり、心配事で胸が苦しくなって眠れなくなったり、そんな経験は、誰しもあるのではないでしょうか。
そんな“こころ”をつかさどる「心(しん)」は、暑さによってパワーが弱まるため、やる気や元気を消失したり、ソワソワして落ち着かない気持ちになったり、眠りが浅くなったりと、暑い夏は、こころ(精神や睡眠)の不調があらわれやすくなります。
⚫︎消化器系の不調
日本の夏は高温多湿のため、暑さだけでなく、湿気も体にたまりやすくなります。
なかでも湿気の影響を受けやすいのが、胃腸の働きです。
そのため夏場は、食欲が出ない・消化不良・下痢など、胃腸の不調に悩まされる方も少なくありません。
また、胃腸の働きが落ちると、エネルギーや血といった栄養をうまく生み出せなくなり、だるさや疲労感など、いわゆる“夏バテ”症状が出たり、体が弱って免疫力の低下につながることもあります。
小暑の暮らし方
暑さが続く毎日。この時期は湯船につかるのも億劫になりがちですが、まだまだ湿度が高い日が続くので、湯船につかってじんわりと汗をかく習慣を続けましょう。
また、お風呂上がりにダラダラと汗が出るため、キンキンに冷えた飲み物を一気飲みしたり、エアコンや扇風機にあたって汗を止めようとする方も多いかもしれません。
ですが、できれば汗をしっかり出し切ってから、身体を拭いてパジャマに着替えるよう心がけてみてください。というのも、汗をかくことで、体にこもった「熱」や「湿気」を外に逃がすことができるからです。
最近では、一日中エアコンの効いた室内で過ごす人も多く、暑さを感じているのに汗をかけない状態になっている方も多くみられます。
熱が体にこもったままでいると、「心(しん)」が熱にやられてしまい、夜になっても気持ちが落ち着かず、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなるといったトラブルにつながってしまいます。
また、体にたまった湿気は、食欲不振・消化不良・下痢など、消化器系のトラブルを引き起こす要因にもなります。
こういった不調を防ぐためにも、汗をしっかりかいて熱や湿気をため込まないことが大切です。
そして、もうひとつ気をつけたいのが、毎日の食事です。
この時期は、夏バテ対策として、スタミナ料理をとる方も多く見られますが、実はそれが、かえって逆効果となり、夏バテを引き起こしているのです。
たとえば、ニンニクの効いた料理などは、食べた直後は一時的に元気が出るように感じますが、胃腸に負担をかけるため、結果的にエネルギーや血を十分に生み出すことができず、体が弱ってしまい、夏バテを引き起こしてしまいます。
もちろん、疲れやだるさを感じていない元気な状態であれば問題はありませんが、湿気が高い今の時期は、〝脂っこいもの〟や〝味の濃いもの〟は控えめにして、消化に負担のかからない「あっさりした食事」を意識することが大切です。
小暑に食べると良いもの
⚫︎牡蠣
精神をつかさどる「心(しん)」に作用する牡蠣には、こころを落ち着かせる「安神(あんじん)」の働きがあり、精神不安や不眠などの不調によいとされています。
牡蠣といえば生牡蠣も美味しいのですが、できれば殻ごと鍋に入れて蒸し、殻にたまった汁ごと味わうのが漢方的には理想です。
牡蠣の貝殻は、動悸や不眠といった症状に古くから漢方薬の材料としても使われていることからも、殻ごと調理し、染み出たエキスまでまるごといただくのが、より効果的な食べ方といえます。
とはいえ、牡蠣はなかなか頻繁に食卓に並ぶ食材ではないかと思います。そんなときにおすすめしたいのが、アサリです。アサリにも、牡蠣と同じく「安神」の働きがあり、こころが乱れやすく不眠になりやすい夏のケアにとり入れたい食材のひとつです。
私自身も牡蠣を頻繁に食べる機会は少ないため、夏の「心(しん)」ケアには、アサリのお味噌汁や酒蒸しをよくいただいています。
⚫︎えだ豆
夏の疲れやすさや食欲不振に悩んでいる方に、ぜひおすすめしたいのが枝豆です。
高温多湿のこの時期は、冷たい飲食や湿気で胃腸が弱りやすく、エネルギーや血といった栄養をうまく作り出せなくなることで、だるさや夏バテのような症状が出やすくなります。
そんな時に頼りになるのが、胃腸の働きを助けながら、体に必要な「気(エネルギー)」や「血」を補ってくれる枝豆です。
さらに枝豆には体にたまった湿気を外に追い出す「袪湿(きょしつ)」の働きもあり、むくみや重だるさも解消してくれます。
夏といえばビールのおつまみのイメージが強い枝豆ですが、実はこの時期の養生にもぴったりな夏の心強い味方ですので、旬の美味しい枝豆をおやつや副菜に取り入れてみてはいかがでしょうか。